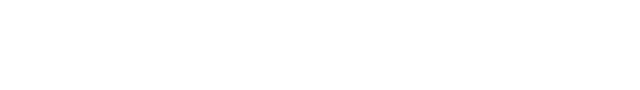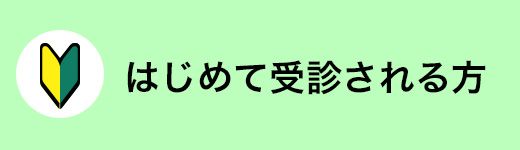一般財団法人永瀬会 松山市民病院様
「コンテンツがとても面白く分かりやすいと感じています。経営やコーチング、個人情報など幅広いテーマを「なるほど」と思いながらメモを取りつつ視聴しているほどです。職員には必修コンテンツの視聴後に感想を書いてもらっています。そこで得られた意見や気づきは数多く、すべてを記録として整理し、大切に保管しています。」
Q. Waculbaを導入いただいた背景をお聞かせください。
当院では、医療職に比べて事務職が学ぶ機会を得にくいという課題を感じていました。医療職は学会や研修に参加する仕組みが整っている一方で、事務職にはそうした枠組みが少なく、自己研鑽の場が限られているのが現状です。
また、従来の研修は都市部で開催されることが多く、参加には移動も含めて時間や費用がかかるため、幅広い職員に機会を提供することが難しい側面もありました。結果として、限られた職員だけが参加し、内容を周囲に伝える必要があるなど、負担が大きい点もありました。
その点、Waculbaはオンラインで場所や時間を選ばず受講できるため、コスト面・効率面の両方で非常に有効だと考えました。一般職や若手職員も含めて学べる環境を整えられることが導入の大きな決め手になりました。
Q. Waculba導入から約1年半経ちましたが、職員の方々の反応や変化はいかがですか?
コンテンツがとても面白く分かりやすいと感じています。経営やコーチング、個人情報など幅広いテーマを「なるほど」と思いながらメモを取りつつ視聴しているほどです。
職員には必修コンテンツの視聴後に感想を書いてもらっています。そこで得られた意見や気づきは数多く、すべてを記録として整理し、大切に保管しています。
特に、自分の業務領域を超えて新しい分野に触れるきっかけになっている点は大きな成果だと感じます。また、すべてのコンテンツを自由に視聴できるようにしているため、必須・推奨を示しながらも、職員が自ら関心のある動画を選んで学べる仕組みになっています。これにより、自分の役割やキャリアに合わせて主体的に学びを深める姿勢が広がっています。
Q. 必須や推奨についてどのように運用されているのでしょうか?
必修として設定したコンテンツについては、基本的に全員が受講を完了しています。昨年は1テーマにつき1か月間で設定し、コンテンツの視聴に加えてレポート提出までを義務化しました。スケジュール調整が必要な場面もありましたが、フォローを行うことで最終的には全員が提出を完了しています。
今年は役職者を対象に、1テーマを2か月間かけて学ぶ形式としています。1か月目に視聴、2か月目に少人数で意見交換を行うことで、共通の学びを起点に互いの考えを共有できる場をつくりました。役職者は日頃、相談や情報交換の機会が限られることもあるため、この仕組みが「同じ立場の者同士で気づきを共有する機会」として活用されています。
さらに、必修課題についてはディスカッション後に感想を提出してもらい、私から個別にフィードバックを返しています。一方通行の「やらされ感」にならないよう、学びを深め合う双方向の仕組みづくりを心がけているところです。
感想文では「どれだけプラスアルファの学びを取りに行っているか」を重視しています。例えば、自分の職務領域を超えて、経営や人事など他部門のテーマにも関心を持って視聴しているかどうかです。実際にそうした越境学習に取り組む職員も少数ながらおり、その姿勢が職場全体の刺激になっています。人数としては全体の数%程度ですが、その一歩が広がっていくことに大きな意味があると感じています。“プラスアルファ”の取り組みが生まれれば十分価値があり、こうした小さな反応や気づきが積み重なることで、組織全体の学びや変化につながっていくのではないかと考えています。
Q. 視聴後のディスカッション(法人内Waculbaゼミ)の運営はどのように設計していますか?
まず大切にしているのは「とにかく集まること」です。所要時間は20〜30分程度と短めですが、気軽に参加できる場にしています。運営側で行うのはグループ分けや期間の区切り、視聴コンテンツの指定までで、司会や進行役は特に決めず、あとは参加者に委ねています。流れとしては「見る → 集まって話す → 感想文を提出」というシンプルなものです。
ディスカッションは“答えを出す場”というより、共感や気づきを得る“きっかけの場”と位置づけています。同じ階層の職員4人でグループを組み、できるだけ部署が重ならないように編成することで、日常業務では接点の少ない人とも意見交換できるようにしています。そうすることで、「同じ立場で同じような悩みを抱えている」と実感し合えることを狙っています。
内容そのものはあえて細かく把握せず、提出される感想文を通じて参加者の学びを確認しています。感想文はコンテンツの所感でもディスカッションの要点でも良いとし、自由度を大切にしています。その中で、昨年は組織に対する意見が多く出る場面もありましたが、それも率直な声として受け止めつつ、「本来は自分自身の行動や役割をどう見直すかに結びつけてほしい」というメッセージを返しています。こうして一人ひとりに想いをフィードバックすることで、自由な意見を尊重しながらも学びの方向性を共有できるようにしています。
まだ始めて間もない取り組みのため、具体的な成果の見極めはこれからですが、職員同士が率直に話し合い、共感を重ねる場として少しずつ浸透してきていると感じています。
Q. 今後、Waculbaをどのように活用していきたいですか?
職員一人ひとりの声をしっかり聞くために、昨年から課長との週1回の1on1(各30分)を始め、今年は係長にも広げました。そこで気づいたのは、多くの職員が自分の成長や学びについて真剣に考えているということです。部下の育成に悩んでいる人、自分自身の次のステップを模索している人など、それぞれが前向きな課題意識を持っていることが分かり、対話の場を設ける大切さを改めて感じています。
現在は面談とWaculbaの学習コンテンツは直接リンクしていませんが、今後は階層ごとに気づきを共有し合えるような仕組みも検討していきたいです。業務に直接関係のないことでも、例えば家族の介護や資格取得への挑戦など、さまざまな話題が出てきます。基本的には「まずやってみよう」というスタンスで応援しており、特に事務職の新しい挑戦は大きなコストもかからないため、意欲を尊重してチャレンジできる環境を整えています。
また、地方には地方ならではの環境があります。松山市にいると、首都圏や関西圏と比べて新しい情報や事例に触れる機会が限られることもあります。だからこそ、Waculbaのように全国の医療機関の取り組みや最新のテーマを知ることができるサービスは大変価値があると感じています。
今後は、経営や組織運営の基本に加えて、DXや業務効率化の事例、他院が直面している課題や解決の工夫など、幅広い情報に触れられることを期待しています。そうした知識を積極的に取り入れることで、地域特有の課題にも柔軟に対応し、組織全体として成長していけると考えています。