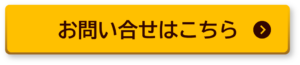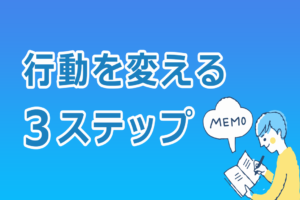目次
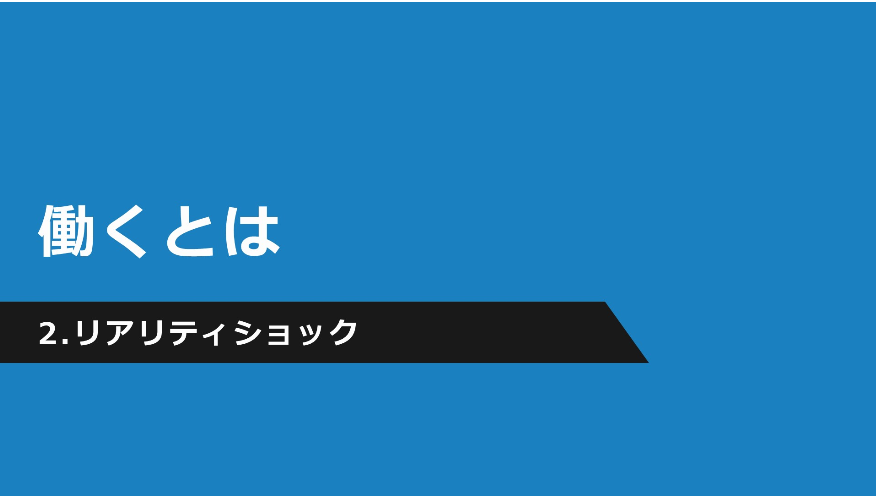
学生から社会人になりたての時や、新しい職場で働き始めた時には、思っていたより大変な仕事や、思っていたより難しい人間関係に悩むことがあります。
社会人になってからの一年間は、入社前に抱いていたイメージとのギャップ、リアリティショックに陥りやすいと言われています。
本記事では、これから社会人として働く方やこれから社会人となる方のために、いずれ来るかもしれない『リアリティショック』の乗り越え方について、リアリティショックが起こる原因とその対策についてご紹介します。
今からその正体を知り、自分をコントロールしておきましょう。
1.リアリティショックとは?
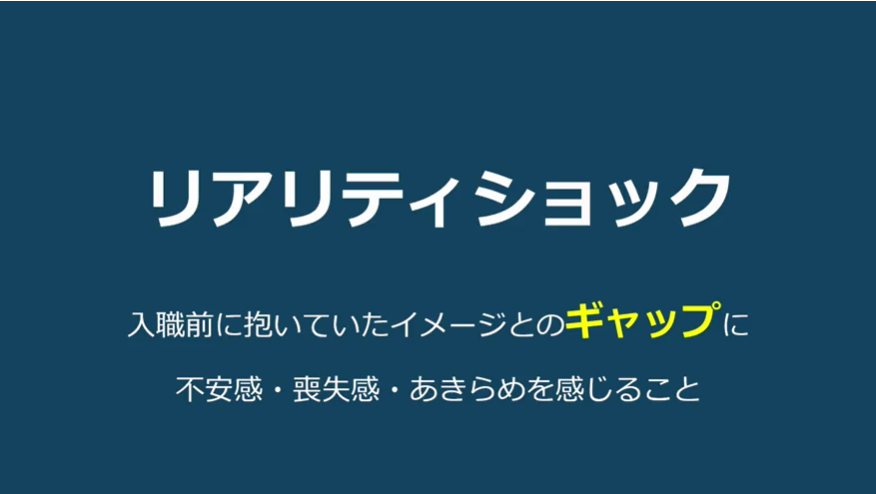
学生から社会人になりたての時や、新しい職場で働き始めた時には、思っていたより大変な仕事や、思っていたより難しい人間関係に悩むことがあります。
こうした、入職前に抱いていたイメージとのギャップに不安感・喪失感・あきらめを感じることを『リアリティショック』と言います。
特に、社会人になってからの一年間は、入社前に抱いていたイメージとのギャップ、つまり「リアリティショック」に、陥りやすいと言われています。
2.リアリティショックが起こる原因
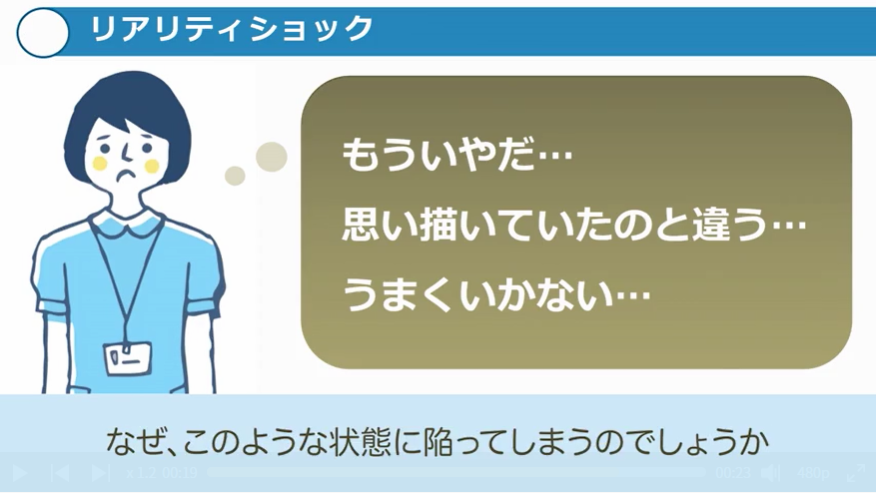
では、そもそもなぜ私たちは『リアリティショック』の状態に陥ってしまうのでしょうか?その原因を考えてみましょう。
学生と社会人の違い
まず、学生と社会人の違いを考えてみましょう。様々な人が暮らす広い社会の一構成員として見れば、学生時代は文字通り 「誰かから学びを得る期間」と言えます。
一方で社会人は、今までの学びを活用して、「誰かに価値を与える期間」と言うことができます。これだけでも、役割が真逆であることが分かります。
学校での立場と、働く場での立場
次に、組織の構成員として見ると、学校での学生の立場は、自由で責任のないものでした。テストの成績が悪くても、その責任を取れと言われることはありませんでした。
しかし、会社や組織の中にいる社会人には、それ相応の責任があります。特に病院で働く人は、患者さんの命を預かる立場であることから、他の業種に比べて責任が重いと感じるかもしれません。
自分の働きが評価され、それで給与が決まるところもあります。
このように、社会人は、学生とは全く異なる役割を担い、責任を背負っているため、そこにストレスを感じることは、ごく自然な反応と言えるのです。
3.リアリティショックの具体例
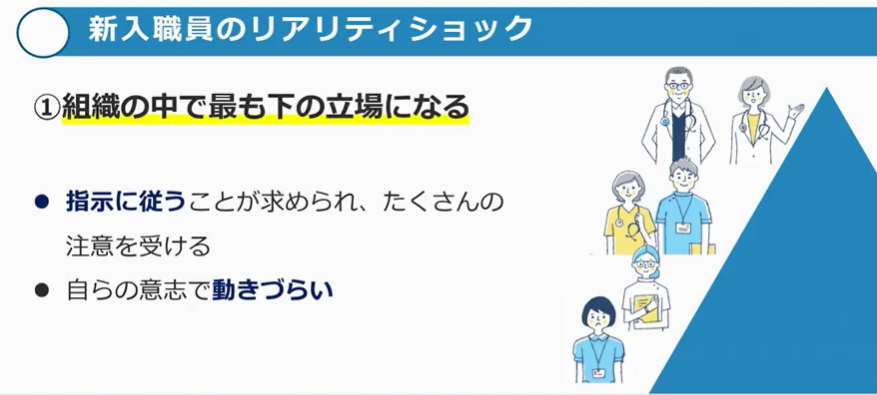
では、実際の現場では、どのようなリアリティショックが発生するのでしょうか?
新入職員に発生しやすい具体例を見ていきましょう。
3-1. 組織の中で最も下の立場になる
新入職員は、組織の中では最も下の立場になります。
そのため、上司の指示に従うことが求められ、たくさんの注意を受けることもあるでしょう。
自らの意志で動きづらいことが、ストレスになってしまうのです。
3-2. 未知の世界でのチャレンジ
新入職員は、学生時代とは勝手の違う世界で、初めての業務を行います。
時間感覚、身だしなみ、ふさわしい態度など、たくさんの新しいルールや規則の中に、自分を合わせていくだけでも大変です。
さらにその中で、慣れない業務を覚えていくことは、どんな人にとってもストレスになり得ます。
3-3. 年齢層、価値観が異なる人々との協働
組織には色々な人がいて、その人々と協働することが求められます。
可愛がってくれる人がいれば、きつく当たる人もいます。
人によって指示に差があることもありますし、マニュアルと異なる指示を受けて、戸惑うこともあるでしょう。
3-4. 仕事のトラブルは日常茶飯事
慣れない仕事なので、大なり小なり、トラブルは日常的に発生します。
患者さんとの人間関係トラブルはもちろん、少しのヒヤリハットやクレームが、命に関わる事故にも発展しかねません。
4.リアリティショックから抜け出すための対策
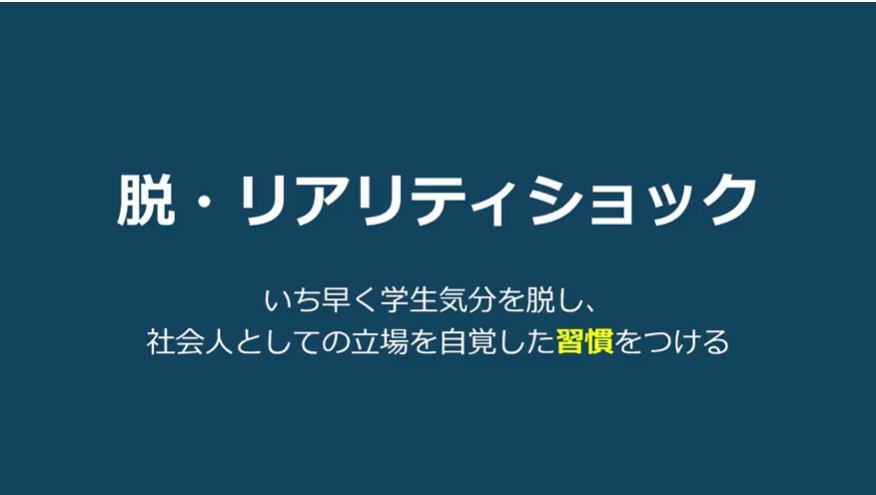
『リアリティショック』に陥ってしまうことは誰にでもあり得ることであり、その状況から早く抜け出すことが、働く上では必要となります。
では、一体どのように『リアリティショック』から抜け出せばよいのでしょうか?
『リアリティショック』から抜け出すためには、いち早く学生気分を脱し、社会人としての立場を自覚した習慣をつけることが大切です。
そのためには、職場に限らず、今の生活そのものを見直してみるとよいでしょう。
いくつか見直しポイントをご紹介します。
4-1. 経済的に自立しているか?
経済的に自立するために、貯金することを意識しましょう。
実家暮らしであれば、家賃や食費を渡す、ということが大きな目安になります。
4-2. 時間を守っているか?
次に、ふだんから時間を守る習慣を身に着けましょう。
例えば、友人との待ち合わせ時間を守る、自分で決めた時間にゲームをやめる、というような心がけで、時間に対する考え方を身に着けることができます。
4-3. 健康管理をしているか?
また、健康管理も大切なポイントです。
夜ふかしは控える、健康的な食生活を心がける、運動を意識するなど、日ごろから自分をコントロールするようにしましょう。
4-4. 前倒し行動を取っているか?
予定の5分前までに行動する、といった前倒し行動を身に着けましょう。
習慣化にはトレーニングが必要ですが、一度習慣化してしまえば、メリットは大きいです。
細かなタスクを後回しにせず、すぐに実行することがポイントです。
4-5. 毎日学習しているか?
最後に、学習の習慣をつけましょう。
社会人では、学んだことを現場で実践することに意義があります。
医療の現場では、学んだことを次の日から患者さんに提供することができます。
毎日少しずつでも本を読む、10分間振り返りタイムを設ける、などの工夫で、習慣化していきましょう。
5.リアリティショックを乗り越えるために大切なこと
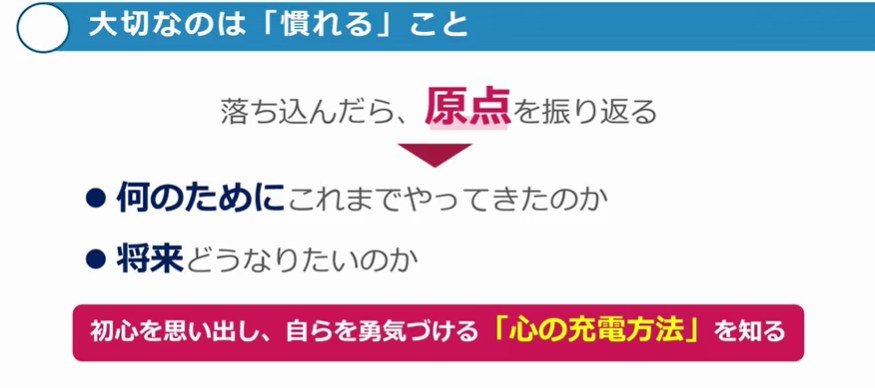
『脱・リアリティショック』には3年かかると言われています。
リアリティショックを解消し、仕事の楽しさを実感するまでの期間は、概ね3年が目安と言われています。
3年も経っていないが、「辞めたい…」という想いが強くなったら、苦しみから逃れたい一心で、安易に「ここではないどこか」を追い求めてしまっていないか、もう一度自問してみてください。
いち早く仕事に慣れるために、まずは、当事者意識を持って、目の前の仕事に打ち込んでみましょう。
組織の一員になりきり、主体的に取り組むことで、自ずと技術と裁量が上がり、仕事が楽しくなります。
また、仕事をしていれば、患者や上司から怒られたり、失敗したりすることは、誰にもあります。
そんな時は、改めて原点を振り返ってみましょう。
何のためにこれまでやってきたのか、将来どうなりたいのか、といった初心を思い出し、自らを勇気づけるのです。
7.まとめ
そして最後に、職場には、応援してくれる同僚・先輩・上司が必ずいることを思い出してください。
ひとりで抱え込まずに、何でも相談できる「仲間」を見つけ、支援し合うことができるといいですね。
今回は『リアリティショック』の実態と、その克服方法についてご紹介しました。
誰もが経験し得ることですので、克服法を実践しながら、いち早く『リアリティショック』を抜け出せるようにしましょう。
なお、「働くとは」コースには、他にも働くことの基本を学べる動画を複数ご用意しています。ぜひ視聴してみてくださいね。
▼サンプル動画はこちら▼